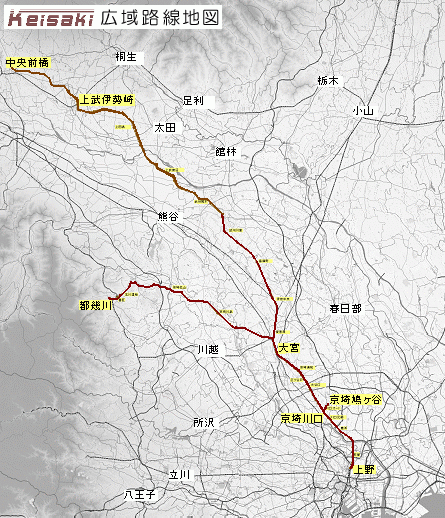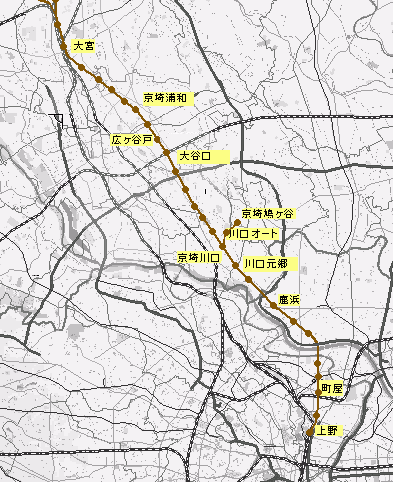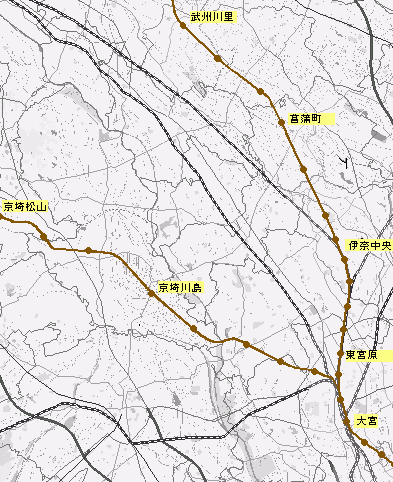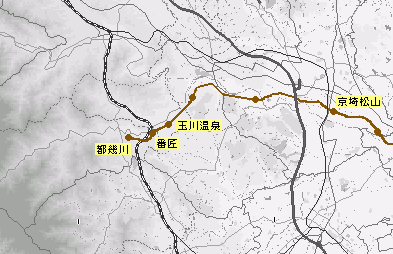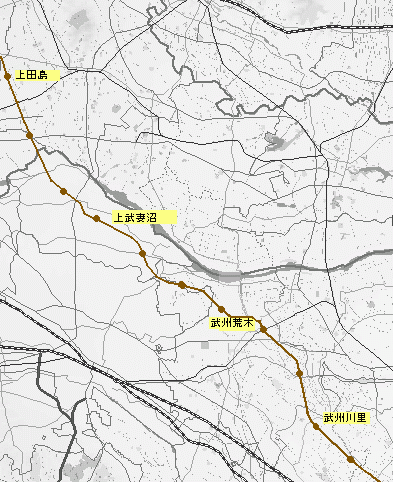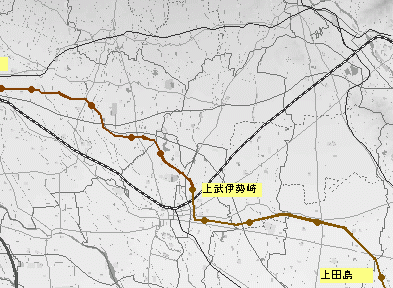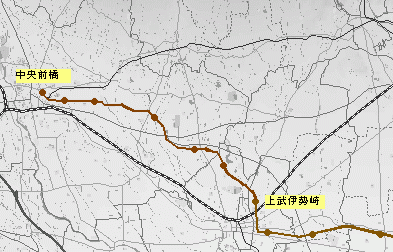どこを走らせようが、「架空鉄道なんだし・・・」という話もありますが、往々にして自宅近所に線路を敷いて路線図や
どこを走らせようが、「架空鉄道なんだし・・・」という話もありますが、往々にして自宅近所に線路を敷いて路線図や
配線図を作っておしまい、となりがちです。「ありそうな私鉄!」を目指すならば、この際「エゴ」はカットで線路を
敷いてみることが大事かもしれません。
ターミナル(山手線のどこかの駅) - 住宅地 - 業務核都市 - ニュータウン - 小都市 - 著名な観光地(温泉?) - 海・山などのロマンあふれる終着駅(笑)
●路線解説
上野-大宮
大宮-武州川里 大宮-京埼松山
京埼松山-都幾川
武州川里-上田島
上田島-上武伊勢崎
上武伊勢崎-中央前橋
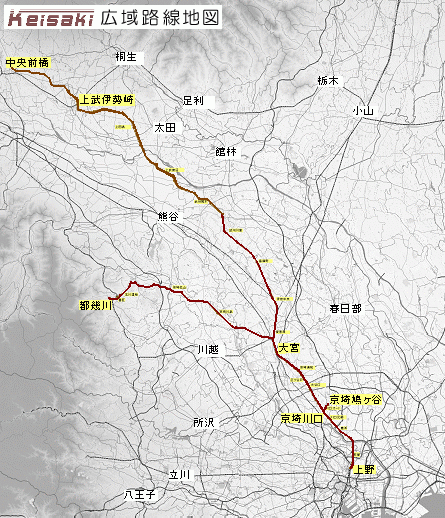
Ⅰ.おおまかな路線選定
架空鉄道用の地図は地形図や道路地図が最適だったりします。道路地図だと建物が詳細です。
どことどこを結ぶにせよ、実世界での設定ならば、ゴルフでグリーンの芝目を読むかのように地図をたっぷり見ながら、路線がフィットするようにします。
こだわっている点を紹介したいと思います。
①地形に沿う(河川、沼池湖)
建築技術が向上したとはいえ、河川を斜めに橋をかけるケースはあまりないと思います。極力最短で橋を設定します。
と、なるとその前後にカーブが多くできてしまうので、さらに手前から緩やかにカーブしながら、アプローチします。
②地形に沿う(丘陵・山など)
丘陵・山地域は、線路のアップダウンが激しくなるだけなので、なるべく安定した台地や谷沿いどおしを結ぶようにします。
33‰の連続じゃキツいですからね(笑)。北越急行みたいにトンネルだらけというのもありですが・・・。
③他の鉄道路線との接続
JR線に這うように私鉄を走らせるケースがありますが、テリトリーを守るために大手私鉄路線に他の私鉄が食い込むことはあまりありません。
地域密着型こそが私鉄の特徴なので、他私鉄路線との交点はなるべく最小にします。
「我田引水」ならぬ「我田引鉄」(笑)
そして、「持ちつ持たれつ」の関係が重要なので、急行停車駅などの主要駅に連絡します。
ターミナルの設定は、都心部へのアプローチを考慮します。
JR-東武の関係でよく見られる、JRの駅に寄り添うようにカーブしてアプローチというケースもありますが、
それだけに固執すると、S字カーブが増えてしまうので、極力直交でクロスオーバーにしています。
④分岐線・盲腸線など
幹線のルートが決まると、分岐線・・・といきたいところですが、ガツガツしないで1路線を暖めましょう。
⑤著名都市、観光地、レジャー施設との関係
行楽輸送などのために、施設のまん前に駅の設定をすることが望ましいですが、線形を大きく変えてしまうなら、そこでようやく盲腸線の出番です。
ただ、これ見よがしに大規模施設を突っ切るのは、非常に大人げないので避けたいとこです。
Ⅱ.駅・駅名の設定
集落や周辺道路との位置関係で駅を決めますが、この時点で駅名を決めることが多いです。
「新○△」とか、地名に由来しない例は、東海道新幹線や武蔵野線などで見られますが、なんだかドライな感じなので、
地図をよくみながら、町名、バス停や字名、小学校名などに地域固有の表現があるので、うまく活用したいところです。
他の鉄道やJRなどで存在する駅名がある場合、旧国名や社名を振ったりして、独自性を持たせます。
○○ヶ丘とかは、どうしても浮かばない場合の最終手段です(笑)。
●路線(上野-大宮) 停車場一覧
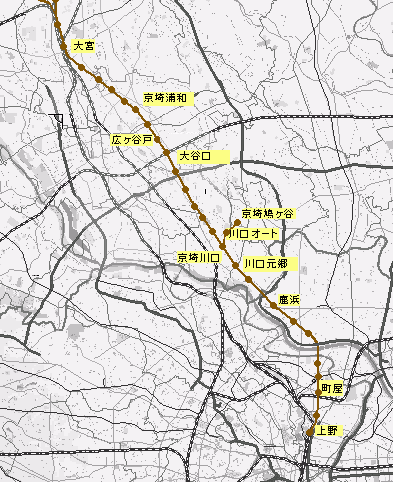
駅間距離が短いことがこの区間の特徴。
歴史的経緯から、当初は下谷(現在の東日暮里に相当)が始発駅であったが、今日は上野駅の地下に
京埼電鉄ホームは存在する。
上野を出ると町屋を経て、隅田川と荒川を渡り、足立区南部から川口市に至る。
岩槻街道との交点に川口元郷。埼玉高速鉄道と地下鉄南北線との乗り換えが可能である。
京埼電鉄の原点である京埼川口からは、盲腸線が京埼鳩ヶ谷に向かう。
JRの川口とは距離が離れていて、賑わいもJR川口ほどではない。
川口線は、鉄道空白地帯でもある、鳩ヶ谷市内からの軌道系交通機関として成り
立っていた。埼玉高速鉄道の開業によって輸送量は減衰しつつあるが、川口オートへ
の波動的な定期外輸送需要もあるため、廃線の憂き目を見るには至っていない。
大谷口はJR武蔵野線との交点に存在するが、JRには駅が存在しない。駅が開業したと
きに、優等種別の列車が停車することも考えられている。
京埼浦和は京埼電鉄の本社が存在し、昭和46年に登場した京埼百貨店と近年ショッピ
ングモールが完成し、県庁所在地が存在するJR浦和とは一線を画した発展をしている。
京埼の大宮側は、かつてはJRとは接していなかった。蓮田方面への路線を指向してい
たためと言われているが、昭和30年代にJRや東武との連絡のため大宮への乗り入れを
果たした。
以来、JR東北線と都市間インターバンの競争関係にあるが、対上野では料金・所要時
間で上回るものの、トータルでは埼京線を含め、線路容量などでJRが優位に立ってい
る。ルートに多少の差があるため沿線サービスに力を入れ、上野-大宮の途中駅で丹念
に利用者を獲得する方針に転換しつつある。
●路線(大宮-武州川里 大宮-京埼松山) 停車場一覧
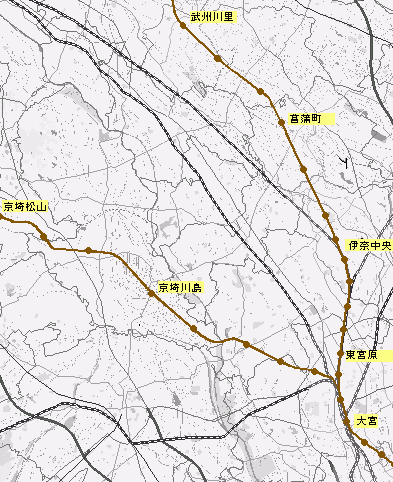
大宮を過ぎると徐々に東武伊勢崎線との距離が近くなるが、菖蒲町まではインフラが
高規格の線路になる。これは東北・上越新幹線との建設に併せて、ニュータウン路線
を同時に建設したためである。伊奈中央は輸送量の分界点になる。
菖蒲町から先は、かつての利根軽便鉄道の名残がある線区になる。駅間が長くなり、
見沼代用水に沿って台地の谷間を利根川方向にすすむ。
かつての中央軽便鉄道が行田方面への路線を断念したのは、高台を超えることが難し
かったためであると言われる。
本線は大成から線路を西へ振り、再び荒川を越える。
かつては田園地帯の単線を2両編成の電車が走る路線であったが、戦後、沿線にも住宅が増えた。
京埼川島は広大な車両区と検修設備をもつ。
●路線(京埼松山-都幾川) 停車場一覧
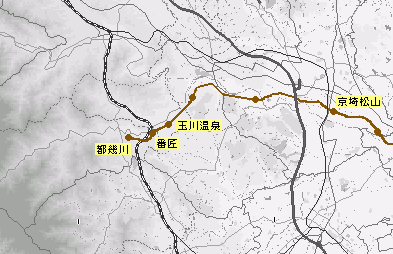
京埼松山からは都幾川沿いに西へ向かう。駅間距離が長くなり、単線区間になる。
路線も狭隘な山岳線区となるため、カーブが続く。特急列車がわずかに発着するが、
ビジネス需要というよりは、長距離利用客の需要に応じて設定されている。
番匠でJR八高線を超え、定峰峠へ通じる山間の入り口に終点の都幾川が存在する。
●路線(武州川里-上田島) 停車場一覧
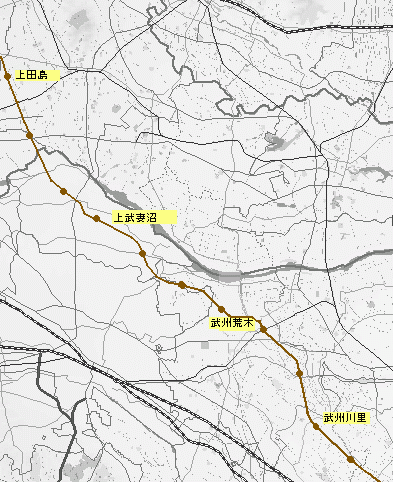
武州荒木では秩父鉄道と連絡する。東京からの通勤圏としてはこのあたりが限界と考
えられ、ここから先さらに輸送量が段落ちになる。
かつては武州荒木から利根大堰のあたりまで砂利運搬用の路線が延びていたが、
現在は存在しない。ここからはかつての上武電気鉄道区間となるため、カーブがつづく。
男沼から利根川を渡り、備前島へつづく。東武伊勢崎線をオーバークロスするが、
駅の設置はされていない。
●路線(上田島-上武伊勢崎) 停車場一覧
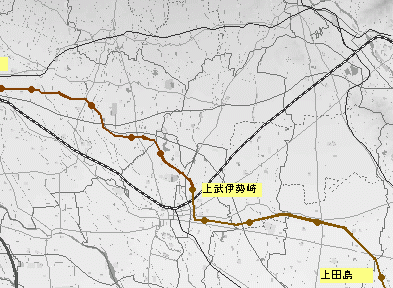
植木町-上武伊勢崎でほぼ直角に曲がり、両毛線をオーバークロスし
上武伊勢崎へ到達する。
京埼電鉄の特急は対東京では優位にあるが、
特急りょうもうは春日部、久喜、羽生、館林、足利を経て太田からさらに伊勢崎へと
北関東の主要都市を丹念に拾うため、ビジネス特急として成り立っている。
対東京ではライバル関係にあるものの、相互に乗客の乗り換えなどは小規模な
ため、暗黙の棲み分けができている。
●路線(上武伊勢崎-中央前橋) 停車場一覧
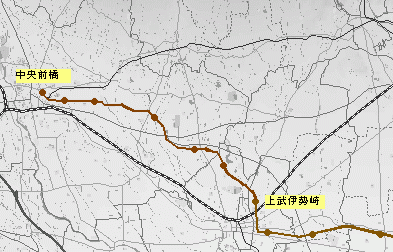
ふたたび両毛線から離れ、カーブを曲がりながら中央前橋へと到達する。
前橋市の市街地に入ると、駅間距離が短くなる。

 どこを走らせようが、「架空鉄道なんだし・・・」という話もありますが、往々にして自宅近所に線路を敷いて路線図や
どこを走らせようが、「架空鉄道なんだし・・・」という話もありますが、往々にして自宅近所に線路を敷いて路線図や