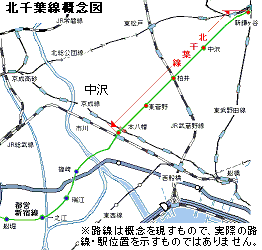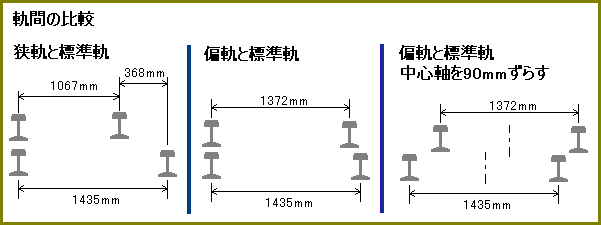上記のように、鉄道事業も公共事業の見直しの一つとして、廃止になっている。これは、入居率が伸びない千葉ニュータウン
までの通勤輸送とするにしても、ただでさえ北総線は日中は各駅停車に限れば、一時間3本程度の輸送力で済んでいるにもかかわらず、
これに加えて、北千葉線は必要ないとされているからである。小室-新鎌ヶ谷を削除して路線の重複が無いように、残る新鎌ヶ谷-本八幡を
結び建設費を圧縮しつつ、千葉県内の交通網の充実と地域の鉄道空白地帯の利便性向上のため、市川市、鎌ヶ谷市が主体となって
「東京10号線延伸新線促進検討委員会」が発足した。しかし、
・少子高齢化などで沿線の人口増が期待できないこと
・約1400億円に上る多額の事業費がかかること、
・事業採算性の見通しがたたないこと、
など、需要と採算性が確保できないことも事業廃止の決め手となり、同委員会の解散により開業は絶望的になり、完全に計画すら無くなった。
ここからはあくまで筆者の私案になるが、都営新宿線が輸送力をまだまだ力を持て余していることなどから、
さまざまな可能性が見い出すことができ、計画如何によっては、まだまだ復活を考えてもよいのではないかとも考える。
●成田空港アクセスとしての新たなルートとして
都営新宿線の延伸は、ファンの間でも論議のネタに挙がる。空港アクセス案や、他にも茨城方面に進む方向や、本八幡から東進し、
西船橋や千葉方面へ伸ばすことも想像できるが、本八幡止まりでは輸送力を持て余すために、こうした議論が交わされる。
成田空港アクセスとして、北総線は成田スカイアクセス線として東に延伸し、成田空港に至った今、同様に北千葉線-新宿線ルートの
もう一つの成田空港アクセスとして、需要を確保するものである。沿線人口増が期待できなくとも、成田空港アクセスとすれば、
必然的に北千葉線は全線乗車になることである。また、東京東部に偏っている成田空港アクセスをより拡げることになる。
新宿から60分程度で成田空港に到達できれば、空港アクセスとして機能できるし、JRの成田エクスプレスより便利になる。
京王からの直通というのもありであろう。八王子や橋本からの列車があれば、東京西部からの利便性が増す。
カバーできる範囲がおのずとJRとの棲み分けにもなるが、空港アクセスとしてのルートとしては良い。
以下では、建設にあたっての問題とその解決方法、開業するとどうなるかについて考えてみたい。
●物理的な問題
まず、成田スカイアクセス線と平行で建設をすると、もちろん需要過多になる。そこで、新鎌ヶ谷から成田スカイアクセス線に乗り
入れるということになるが、分かりきった問題であるが、軌間の問題がある。
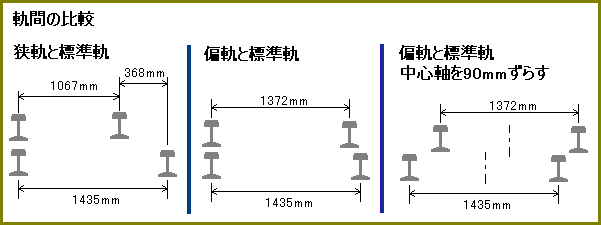
成田スカイアクセス線は、京成押上線、都営浅草線、京急線に乗り入れるが、軌間は(1,435mm)、対する北千葉線は都営、京王の
線路と接続をすることになるが、軌間は(1,732mm)である。
軌間の統一は、既存路線を全面改修することから、特に都心部や地下鉄などでは、多くの費用がかかり、列車の運休をせざるを
得ない点から、各所で難色を示すことは必至であるし、現実的ではない。
軌間の違いを克服する考え方はあり、3線方式で、実際に小田急が箱根登山鉄道への乗り入れで用いられたり、海外でも実例は
ある。
しかし、新宿線の1372mmと浅草線の1435mmの差は、わずか63mmであり、車輪のフランジが干渉するため、この方式では解決できない
(上図の中央)。
中心軸を90mmずらし4線方式(上図の右)としても、路線距離が長大である点から、現行の施設改良から保守運用面まで問題が多い。
このような問題があり不可能と思われるが、これらを解消するために、フリーゲージトレインを導入することもありだろう。
フリーゲージトレインは日本国内では研究・実証段階であるが、海外では既にスペインで2006年から導入されている。
フリーゲージトレイン導入の際は、台車の軌間変更をするため、停車もしくは徐行運転をすることになる。
場所は成田スカイアクセスと北千葉線の接続である、新鎌ヶ谷の駅構内、あるいは接続点手前となろう。
車両は高価になるので、一般通勤型車両の直通は容易ではないため、空港アクセス列車のみを直通とし、
それ以外の列車は全て新鎌ヶ谷で折り返しとなるであろう。
●建設主体はどこに?
千葉県、市川市、鎌ヶ谷市、京成などによる第3セクターによる建設、京成による運営で上下分離方式とすることが妥当だろう。
東京メトロ、都営の経営一元化も進んでいるが、この経営体が加わってもよいだろう。
●開業時はどうなるか?
開業時には、全線を12〜13分程度で運転されることが予想される。一般車は全て各駅停車となるであろう。
通過運転とすると北総線経由より大幅に都心から近く、利用客にとっては利便性が大幅に向上する。
現在のダイヤをあてはめると、朝ラッシュ時6分間隔、日中は20分間隔、夕ラッシュ10分間隔となるであろう。
都心への所要時間の増大となるので、東葉高速の例から、乗り入れ先の優等種別が直通することになる。
急行が直通するようにすれば、新宿-新鎌ヶ谷が40分程になる。ラッシュ時は43分程度になるであろう。
都営新宿線は8両編成または10両編成のため、これがそのまま延長になる。
大多数が京王と直通をするため、走行距離は長大になる。
一般列車の利用客の流れは新鎌ヶ谷の乗り換え利用者がメインになる。東武野田線柏方面からは、新宿に出るために
常磐線経由にくらべ、乗換えが最小となるため、利用者が増えると思われる。乗り換え客をベースに本八幡まで漸増
していき、本八幡で総武線に乗り換える乗客と新宿線に直通する乗客に分かれる。沿線に大規模の住宅はないが、か
りに柏井に武蔵野線と乗換えができると、ここにも流れができるが、東松戸がそうであるように、定着するまで時間
がかかりそうだ。途中駅に大規模住宅群が沿線にないため、突出した乗降客数の駅はないであろう。
特急は全線通過運転となり、停車駅は、新宿-市ヶ谷-神保町-馬喰横山-本八幡-新鎌ヶ谷-空港第2ビル-成田空港と
して、40分間隔とするのが妥当である。都心部でむやみに通過運転をしたり、また過度に停車駅を増やすと
速達性と利便性のバランスが損なわれる。
車両は大別して空港アクセス専用の特急車両(フリーゲージ対応)、一般車両の二種類を用意する。
一般車両は都営新宿線で運転されている、10-000形・10-300形・京王9000系に準じた20m4扉となる。
車両の保守や管理のため、自社で車両を持たない可能性もある。
北千葉線側で車両を用意する必要があるとすれば、特急車両のみとなり、これはフリーゲージトレイン
とするほうがよいであろう。車体長は京成スカイライナーと同等になるか、都営・京王の標準である20m級とするかの
いずれかになるが、後述のとおり、ホームドアの問題も出てくるので、20m級がよいだろう。
●車両と検修
車両の保管・保守点検等は、自線内で検修設備を備えるのはコストがかかるため、都営もしく
は京王に委託をするか、フリーゲージトレインでもあるため、北総公団線側で検修を行うようにしてもよいであろう。
●既存設備の改良
都営新宿線の設備も大幅に改良しないとならない。優等種別が頻繁運転するには、都営新宿線内の2面3線の待
避駅を4線として、両線ともに待避ができる形に改良しなければならない。これがダイヤに直接影響を与える。
新宿-本八幡は25分で走破できるように、線路を高速化対応を行い、
駅設備にも改良が必要で、通過列車対策としてホームドアを設置する。
但し、特急停車駅では特急用車両と一般車両にドア位置を合わせるのが今の技術では難しいとされるため、
今後、技術進歩で対応できるようにするか、または20m車両にし、1位と4位を共通にし、2位と3位の開け閉めで調整する
という考え方もできそうだ。
特急券の発券設備や、折り返し駅では車両内トイレなどの汚水処理設備も必要である。
一部であるが、成田スカイアクセスの線路容量の限界もあるため、成田空港付近の単線区間を複線にする必要がある。
●運賃高騰は避けられるか
千葉県内の比較的新しい路線は北総線、東葉高速ともに高額で、運賃設定によっては沿線の利用客が離れていく原因にも
なっており、近年では北総線の運賃値下げをめぐって裁判があった。
建設費、特殊な車両で費用もかさみ、高運賃は避けられない。定期利用客に対しては、大幅な値下げをしなければなら
ないであろう。運賃は低廉にしつつ、補填をするために成田空港アクセス利用者に料金を設定するしかなくなる。
1400億円の費用としても、単純計算で運賃×利用者数とした場合、400円の往復、つまり800円の往復運賃であったとしても約2億人
近い利用客が見込めないと、建設費のペイができない。乗降平均が一日20万人とした場合、1000日、3年余りの期間を要することになる。
しかし、建設費の償還は事業の黒字分で埋めないとならず、債務超過の解消のために20万人の利用者数それ以上の利用がないと債務償還
に追われる赤字路線になってしまう可能性がある。
スカイライナーは日暮里-成田空港で特急料金が2,400円であるが、現在のJRの成田エクスプレスが新宿-成田空港で3,110円
としていることから、これ以下にしなければ、料金面で競争にはならない。現行の運賃形態で考えた場合、JRと同等にする
ためには、新宿-本八幡360円、北千葉線全線690円、成田スカイアクセス線を1,250円、これに特急料金を1,000円としなければ
ならない。北千葉線、成田スカイアクセス線の運賃が高くなるため、いずれにしても高価になるので、このぐらいになると
思われる。
●西船橋方面への延伸はどうか?
以上は延長新線を成田空港アクセスとして活用するものであるが、
需要が少ないことに問題があるならば、ある程度の需要が見込めそうなルートを新たに考えてみたい。
それは本八幡から東に向かい、西船橋に乗り入れる、総武線・東西線の更なるバイパス路線として活用するものである。
総武線(各駅停車)の錦糸町から千葉方面でと連絡する各線をみると、
・亀戸…東武亀戸線
・新小岩…総武快速線
・市川…総武快速線
・本八幡…都営新宿線
・西船橋…武蔵野線、京葉線、東西線、東陽高速線
・船橋…東武野田線、京成線、総武快速線
・津田沼…新京成線
・幕張本郷…京成千葉線
・千葉…房総方面各線、京成千葉線、千葉都市モノレール
である。
乗り換えも充実し、一見便利なようにみえる。しかし、ジャンクションが多岐にわたり、実は利用しづらい。都営新宿線沿線から
東松戸に向かうには、本八幡と西船橋を利用しなければならない。また京葉線方面と総武快速線、野田線との乗り換えも面倒である。
乗り換え結束点がバラバラになることで、相互の移動距離は少ないのに、待ち時間を含めると時間がかかるのである。
利用者は「それならばマイカーで」という結論に達してしまう。
思い切って西船橋を一大ターミナルとして、交通体系を整理し、都営新宿線を乗り入れさせるのも一考ではないか。
こうすることで、混雑緩和が進まない東西線や総武線のバイパスとなる効果もある。
現在も一定のバイパス効果になっているが、本八幡での新宿線と総武線の乗り換えはかならずしも便利とは言いがたいため、
着席目的でもない限りわざわざ都営新宿線に乗る必要がないのである。
ルートとしては本八幡から東進(かなりキツいカーブになるが極力最短で東に向ける)、国道14号の直下を進み、そのまま西船橋に向け
るのである。総武線が西船橋を快速停車駅にすれば、京葉線へのシフトも進むし、東西線は混雑が緩和する。京成西船−西船橋をペデ
ストリアンデッキ等で歩車分離ができるとなお効果的である。結果的に付近の道路の混雑緩和にも寄与できよう。
建設費の問題があるならば本八幡-西船橋に途中駅を設置する必要はない。
西船橋の駅の位置は理想的なのは快速線を整理した上で、地上ホームとして現在の橋上駅舎に最短で接続できるようにする。
場合によっては東京メトロ/東葉高速線の地下にホームを作るのもありではないかと考える。
総武快速線の停車は、快速の混雑がより激化する懸念があるため必須ではないが、停車をするようになれば、より便利である。
都営新宿線は東京都なのでこれを事業化するのは難しい。東京メトロと経営統合あとの建設も考えてよいのではないか。
沿線地域の第三セクターとして船橋市、市川市、千葉県、京成、JRが建設費を負担、運営会社として京成が担うというのもあり
ではないだろうか。東葉高速鉄道の別路線として運営してもよいのではないか。
以上で述べた、延長新線の私案であるが、新宿線を単に都民の足としてではなく、包括的な交通網の整備という観点に
立って延伸に対して積極的になるべきであろう。
単に新線建設とするならば、明らかに無駄な事業であるし、削除したほうが良いケースも多々見受けられ、
千葉県には、これまでも鉄道新線の建設や高速道路の整備の実例があったが、京成千原線にしても、東京湾横断道路にしても、
事前予測を下回るケースが多く、結果として利用料金の高騰につながり、本来であれば料金を抑えられる周辺の路線にまで影響を
うけているもの、また多くの公的資金が投入されていることが多い。極端に言えば、需要喚起のための建設になっていたことが多く、
これらの考えには反対であり、本来、充実を図るべきところを精査しなければならないと考える。
つまるところ空港アクセスにせよ、他にせよ、需要を見出さない限り、新宿線の延伸ないが、これまでの投資効果を無駄にせず活用
していきながら、混雑緩和や利便性の向上を目指すべきではなかろうか。
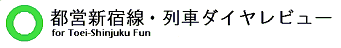
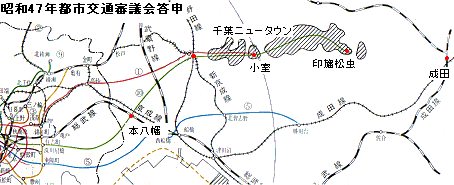 ←左図
←左図