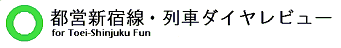| 年月日 |
事柄 |
記事 |
| 1955〜 |
京王線の都心
乗り入れ計画 |
上野線(新宿-飯田橋-上野)、両国線(飯田橋-両国)、麻布(?)線(両国-月島)など
▼当時の東京都電に現新宿線同様のルートの路線が実在していたが、京王は都心乗り入れを
計画していた。計画路線は、現在の新宿線、大江戸線のルートの基礎となるものであった。
▼京王は他に、立川線(富士見ヶ丘-西国立)や相模原線延長線(橋本-相模中野-津久井湖畔-
道志村-都留-富士吉田、富士急行線の改軌もふくめ、長大路線を指向していた)などの路線
を計画していたが、社会情勢の変化などで、実現をしたものや計画頓挫、発展的解消などの
ものがある。
|
| 1972〜 |
開業に至るまで |
運輸交通審議会東京10号線として、東京都による免許線取得
▼当初、京王は芦花公園-新宿の路線として、甲州街道直下に地下鉄線を敷設し、混雑する
一方の京王線の混雑緩和を画策したが、投資効果が現行京王線の減益につながるとの判断か
ら、現行京王線の線増(複々線化)になった。
▼京王側の相互直通運転区間はつつじヶ丘-新宿、普通のみで計画されたが、これは時代背
景として、郊外圏がまだ23区周辺程度であったことと、他線の相互直通運転は普通運転のみ
が主流であったことが考えられる。
▼乗り入れに際し、都は浅草線の京成乗り入れで実績のあった改軌(1372mm→1435mm)を京
王線でも行い、車両の融通を図ることを希望していた。当時、京王側では改軌工事期間中の
優等列車の運転を休止することによる輸送力の低下、工事に必要な用地取得等が困難であっ
たことなどから難色を示し、運輸省までが動く事態にまでなったが、最終的に都側が京王の
軌間で建設をすることになった。
▼10号線は西側を多摩ニュータウンの通勤輸送としてを機能を持つことになり、東側は千葉
ニュータウンの通勤輸送としての機能をもつことになった。岩本町は、京王線からの大運転
列車の発着を見込んでいた。東側では急行運転をする計画もあったが、東西線が当初の予想
を上回る輸送量により、普通の増発を余儀なくされていたことや、公営地下鉄という立場か
ら、緩急運転に対しては慎重であった。
▼千葉ニュータウンは、京葉工業地帯の成功による、その見返りとして、県北西部の印旛地
域に巨大なニュータウンの計画をしたが、オイルショックによる景気の低迷により、ニュー
タウンが縮小した形となり、現在に至っている。
▼北千葉線は用地取得の際、不正があったとして議会での紛糾問題にまで発展し、建設計画
が頓挫し、現在に至っている。
▼かつての敏腕、故・中里江戸川区長の「マジック」がなければ、住吉以東の新宿線の延長
計画はなかったものと言われている。江戸川区内での蛇行が多く見られるのはその影響とも
言われるが、増大する総武線、東西線の乗客輸送の補助としての役割色はこのときから濃く
なり、建設・開業は東側がまず優先された。
|
| 1978/12/21 |
岩本町-東大島開業 |
朝7分間隔、昼10分間隔、夕8分間隔で運行開始。
西側は岩本町の中線、東側は東大島の荒川橋梁の手前までを引き上げ線として、折り返し運転をしていた。
全て6両編成とし、大島に検修区が設置された。
建設にあたり、森下は将来の12号線開業に備え、駅ホーム部分を同時着工していた。
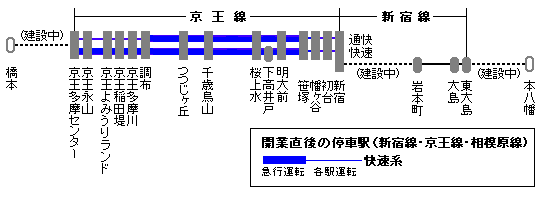 |
| 1980/03/16 |
新宿-岩本町開業
直通運転開始 |
既に開業していた京王新線経由で京王線と直通運転開始。
大運転:快速、通勤快速[京王多摩センター-岩本町] (快速、通勤快速は岩本町の中線で折り返し)
小運転:普通[笹塚-東大島]
朝ラッシュ時は京王線の12分サイクルにあわせ、通勤快速1、普通2の構成、
昼間は20分サイクルに大運転の快速1本、小運転の普通2本の構成だった。
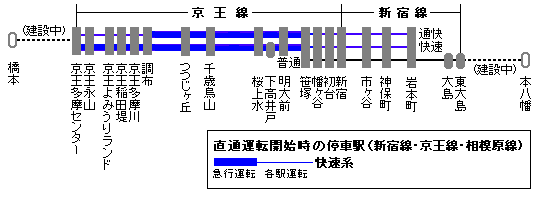 |
| 1983/12/23 |
東大島-船堀開業

|
東大島にあったクロスポイントはそのまま使用され、船堀までは変則単行運転であった。
そのため、船堀には改札構内に次列車発車案内装置があったが、消滅している。
バス・レールシステムの導入。(1999年廃止)
車両増備は行われなかった。 |
| 1984/10/01 |
ダイヤ改正 |
早朝の船堀始発の京王八王子行きが笹塚行きに改められる。 |
| 1986/09/14 |
船堀-篠崎開業
(ダイヤ改正は
1986/09/06)


|
以前は普通が岩本町で列車間隔の時間調整をしていたが、この改正で解消された。
都営車両の8両編成が登場。
瑞江の列車待避設備はこの時点で準備されていた。
篠崎での折り返しは、本八幡寄りのシーサスポイントで行われていた。 |
| 1987/??/?? |
ダイヤ改正 |
早朝の瑞江始発が篠崎始発に改められる。 |
| 1987/12/20 |
ダイヤ改正 |
快速・通勤快速延長運転[岩本町-大島]
8両編成の京王車が大島まで直通するようになった。
笹塚-大島で昼間は実質的に20分に3本になった。大島でも快速が中線で折り返しをしていた。
この頃から、馬喰横山以東で東行きは大島止まりの列車の後の列車が混むようになる。
都営車による京王線の快速列車登場。 |
| 1988/05/21 |
ダイヤ改正
| 京王相模原線京王多摩センター-南大沢開業。
通勤快速の一部が南大沢発着になる。 |
| 1989/03/19 |
篠崎-本八幡開業



|
全線を40分で結ぶ。暫定開業のため、片側ホームは使用されず、
8両編成分、1面のみ使用可能であった。
朝ラッシュ時は最大で10本/hで限界だった。
中間車増備で都営車両は全て8両編成になる。
浜町〜大島はすでに10両延長準備がなされていたが、10両対応になる。
これにより、岩本町発着が始発・終着を除き消滅する。
早朝・夜間に本八幡行きが増発される。
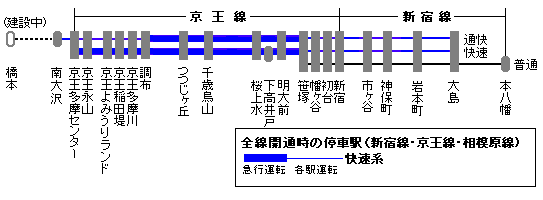 |
| 1990/03/30 |
ダイヤ改正 |
京王相模原線南大沢-橋本開業によるダイヤ改正。
大運転の快速・通勤快速が橋本発着になる。 |
| 1990/10/01 |
ダイヤ改訂 |
京王ダイヤ改正によるダイヤ改訂。 |
| 1991/04/06 |
ダイヤ改正 |
京王相模原線多摩境開業による改正。 |
| 1991/09/01 |
ダイヤ改正 |
快速・通勤快速延長運転[大島-本八幡]
本八幡の本格開業に伴い、10両対応2面使用可能となった。
京成八幡との連絡通路が完成。
船堀〜本八幡が10両対応になり、通勤快速が本八幡発着となる。
この頃は都営車は半数が冷房車両となり、京王車と合わせて、冷房化率約66%であった。 |
| 1992/05/28 |
ダイヤ改正 |
大運転の快速が調布-橋本間各停運転になる。
夕ラッシュ時の桜上水行きが廃止になる。 |
| 1997/12/24 |
ダイヤ改正 |
急行運転開始。新宿-本八幡を最速29分で結ぶ。
急行は平日昼間 新宿-本八幡のみ。停車駅は市ヶ谷、神保町、馬喰横山、大島、船堀。
瑞江は通過列車待避設備があったが、線路が敷設されたのはこの1年ほど前からであった。
岩本町、瑞江で通過追い越しを行い、岩本町で急行は中線を徐行で通過していた。
急行運用は都営車が就いていた。
平日夕ラッシュの大島止まり全てが本八幡まで延長運転。 |
| 2001/03/27 |
ダイヤ改正 |
昼間時を主とする改正。
急行列車の京王線への直通開始。
平日朝ラッシュ時に、通勤快速高尾山口行き、休日に急行高尾山口行きが設定される。
京王線内急行、新宿線内普通の種別が設定される。
直前の2000/12/12に大江戸線環状部が開業し、急行停車駅に森下を追加。
東行き最終に、瑞江行き新設(平休日とも)。
急行の岩本町での追い抜きは外側に改められる。
東行きの快速・通勤快速や種別を変更する急行は、新宿で種別幕の表示を変えるようになる。
八幡山行きが新設される。

|
| 2003/12/01 |
ダイヤ改正 |
朝ラッシュ時を主とする、京王線方面向けの改正。
朝ラッシュ時の西行きの新宿止まりが笹塚まで延長。
夕ラッシュ時に京王線内急行運転の列車設定。
八幡山行き→つつじヶ丘行きの変更。
休日の急行運転拡大。
西行きの朝ラッシュで一部、所要時間が変更(本八幡-新宿で普通40分→43分) |
| 2005/03/25 |
ダイヤ改正 |
夕ラッシュ時を主とする、京王線方面向けの改定。
朝ラッシュ時の西行きの快速橋本行きが急行に変更。
夕ラッシュ時の西行きの快速橋本行きが、調布から急行に変更する種別を新設(表示上は快速調布行き)。
休日の急行運転拡大。
10-300形・10-300R形の就役
|
| 2006/09/01 |
ダイヤ改正 |
京王直通急行・快速の直通列車10連化を主とした改正。
急行の10連化
夜間23時台の東行きの増発
西行き7時台の大島始発が本八幡始発に変更
休日朝に急行多摩動物公園行き(新宿線内は各停運転)の登場
京王車が10両編成に統一され、再び大運転→京王車両、小運転→都営車両になる。
|
| 2011/03/11 |
ダイヤ改正 |
休日朝に急行高尾山口行きの増発
※ダイヤ改正当日に東北地方太平洋沖地震が発生し、軒並み運休が発生した。同3月13日から電力逼迫に伴う日中の本数減による臨時ダイヤとなる。
|
| 2012/08/19/td>
| ダイヤ改正 |
京王線調布駅付近の連続立体交差事業の完成によるダイヤ改正に伴う列車の発車時刻の変更。
|
| 2013/02/23 |
ダイヤ改正 |
京王線ダイヤ改正に伴う列車の発車時刻の変更。
京王線内を急行・区間急行・快速
として運転する列車は新宿で種別変更するように変更。
|