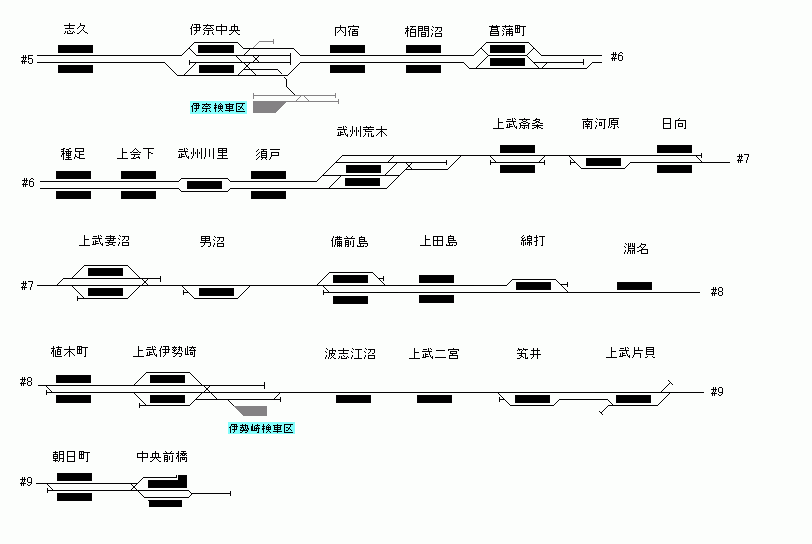配線は地図と情景、輸送量に応じたレイアウトにしています。
配線は地図と情景、輸送量に応じたレイアウトにしています。
●配線について
配線の設定は、高速化を意図してポイントが必要最小限になるようにしている。
軌道時代の影響で相対式ホームが多いことと、部分複々線化をすることで、優等列車待避のロスが減らす工夫をしている。かつて、京埼川口は
平面交差で川口線との分岐をしていたが、立体化が完成し、ダイヤ上のネックを減らした。
貨物輸送時代の配線からの方向転換の整理統合は完了し、遊休設備の売却・関連会社施設への転用としているため、現在は存在しない。
車両搬入の関係で、大宮などで他社線と線路をつなげている。
ホーム有効長は、
上野・大宮が20m級大型車が12両編成分(250m)
その他の上野-武州荒木・京埼松山では全駅10両編成分
唐子ヶ丘-都幾川・大利根-中央前橋・は6両編成分としている。
車庫は輸送量に応じた位置に設定している。集落や住宅街の設置は利便性や近隣への配慮から、必要最低限とした。
大規模車両検修設備は、車両機器の陸送の都合から、閑散地に設定している。
保線設備・保線区は適宜配置している。
■本線(上野-伊刈)、川口線(京埼川口-京埼鳩ヶ谷)
上野は昭和36年の地下ホーム開業当初から乗降分離を意図し、降車ホームが設置されている。
昭和の高度経済成長によって輸送量は大きく増大し、対応策として長編成化がすすめられてきた。
過密ダイヤによって、優等列車のスピードダウンが深刻化してきたため、都心部の複々線化が構想されたが、
南北線開業によって分散されると判断したため、部分的な複々線化が構想された。
鹿浜-東領家
川口元郷-京埼川口
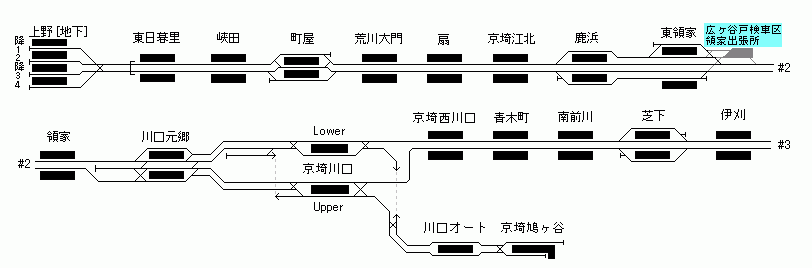
■本線(大谷口-出丸)、大利根線(大成-丸山)
大宮はかつての変則的な地平ホーム時代から機能的な2面4線のホームへと変貌を遂げた。
東武へつながる車両搬入・回送用の接続線が設置されている。
また、区間運転用に上野方に折り返し線が設置されている。
大宮-大成は方向別複々線だが緩急を分けない配線としている。
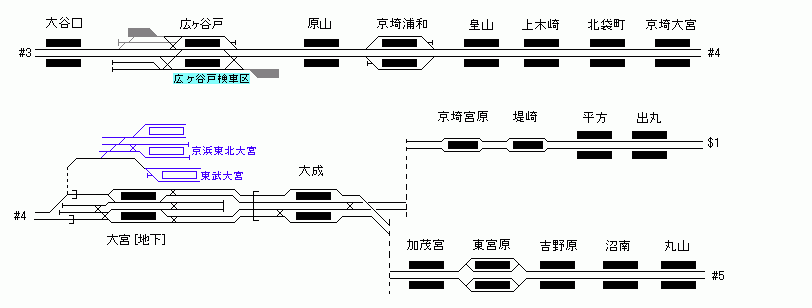
■本線(京埼川島-都幾川)
京埼川島に検車区がある。京埼松山から都幾川までは一部複線の単線区間となる。
番匠はかつて貨物輸送を行っていた時代に入れ替え用の構内線路が設置されたが、現在では保線基地になっている。
都幾川-西平は路盤と線路のみ設定されている。
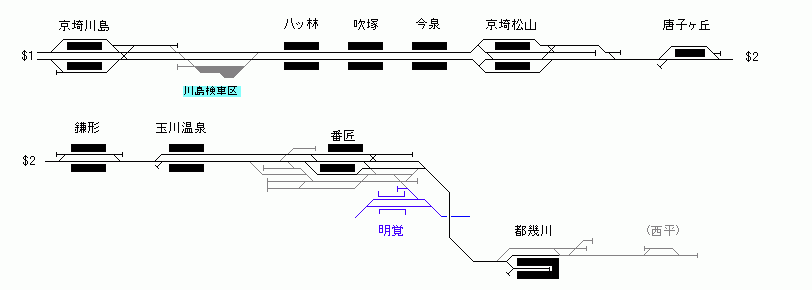
■大利根線(志久-中央前橋)
上武斎条から中央前橋までは一部複線の単線区間となる。
上武伊勢崎に検車区がある。
中央前橋から伸びている線は、延長を意識したものではなく、機関車の入れ替えがあった名残である。