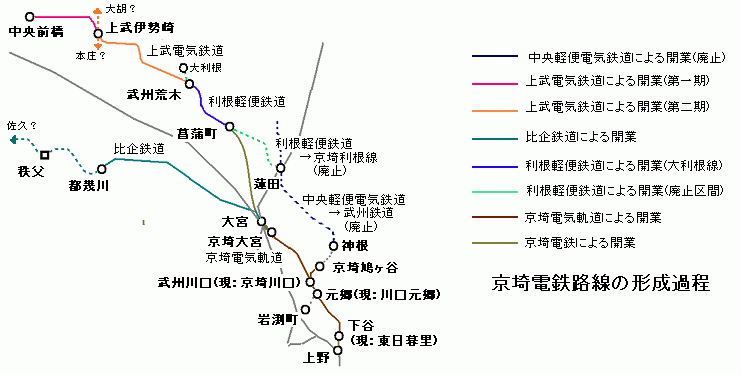| 年 | 京埼電鉄記事 |
|---|---|
| 昭和22 | 下谷-京埼大宮を本線、大宮-都幾川を都幾川線、蓮田-大利根を蓮田線、武州荒木-中央前橋を利根線として京埼電鉄創立 |
| 昭和22 | 京埼鳩ヶ谷-京埼川口 再開、複線化 |
| 昭和25 | 急行運転開始 (下谷、町屋、沼田町、京埼川口、芝下、広ヶ谷戸、京埼浦和、京埼大宮) 軽便線区間廃止(大利根-武州荒木) 都幾川-秩父免許取得。 |
| 昭和29 | 旧武州鉄道区間免許取得(神根-蓮田) |
| 昭和30 | 皇山開業 日中15分サイクルに改正 |
| 昭和31 | 京埼川口-駒込 免許取得(現南北線ルートとほぼ同一)
旧利根軽便鉄道区間(蓮田-武州荒木)を改軌(726mm→1,067mm) |
| 昭和33 | 京埼大宮-大宮 開業、大宮-都幾川と本線の直通運転開始。上野-都幾川を本線とする。 準急運転開始(下谷、町屋、沼田町、京埼川口〜大宮各駅) |
| 昭和35 | 下谷-東日暮里廃止、東日暮里-上野開業、沼田町→京埼江北に改称 停車駅種別見直し(急行:上野、京埼川口、京埼浦和、大宮) |
| 昭和37 | 原山開業、免許区間廃止(神根-蓮田) 伊奈新線(大宮-菖蒲町)免許取得 ダイヤ改正(特急の新設) |
| 昭和40 | 駒込-京埼川口 営団地下鉄に免許譲渡 |
| 昭和44 | 都電との直通運転を休止、川口線(元郷-岩渕町)廃止、京埼鳩ヶ谷-京埼川口を改軌(1,372mm→1,067mm) ダイヤ改正 |
| 昭和45 | 伊奈新線の経由地変更。用地の一部は国鉄用地(東北新幹線)に売却 |
| 昭和46 | 貨物輸送(都幾川-大宮-青木町-京埼江北)廃止 菖蒲町-武州荒木電化 |
| 昭和47 | 大谷口開業、日中15→12分サイクルに改正 都幾川-秩父免許失効 |
| 昭和49 | 伊奈新線(大成-菖蒲町)開業 蓮田-菖蒲町廃止、大宮-中央前橋を大利根線に統合、名称変更 |
| 昭和56 | 大宮地下ホーム竣工、伊奈新線、利根線を統合、大宮-大成高架複々線化 全面ダイヤ改正 |
| 平成2 | 鹿浜-東領家高架複々線開業 |
| 平成3 | 埼玉高速鉄道発足、元郷-浦和大門 埼玉高速鉄道に免許委譲 |
| 平成12 | 営団地下鉄 赤羽岩淵-川口元郷、埼玉高速鉄道 川口元郷-浦和美園 開業 元郷→川口元郷に改称 川口元郷-京埼川口-川口オート、高架完成 通勤急行の新設 |