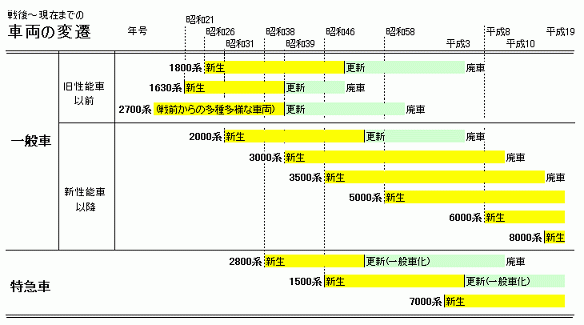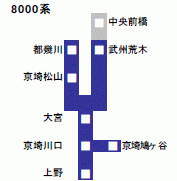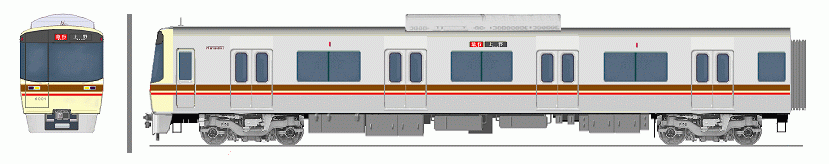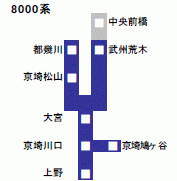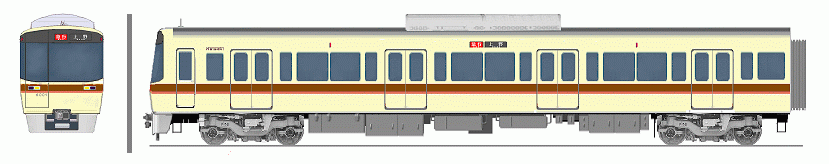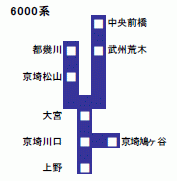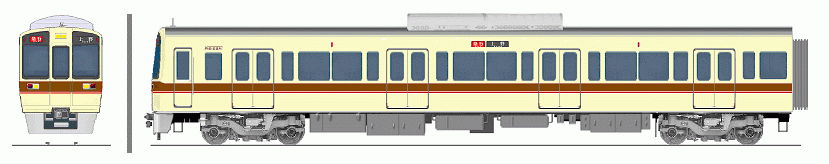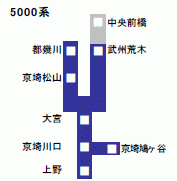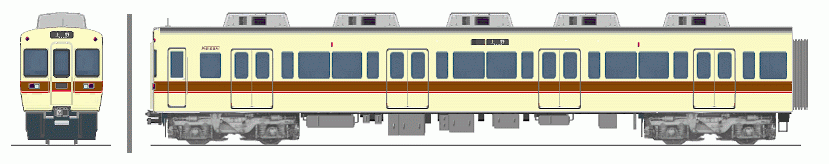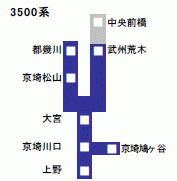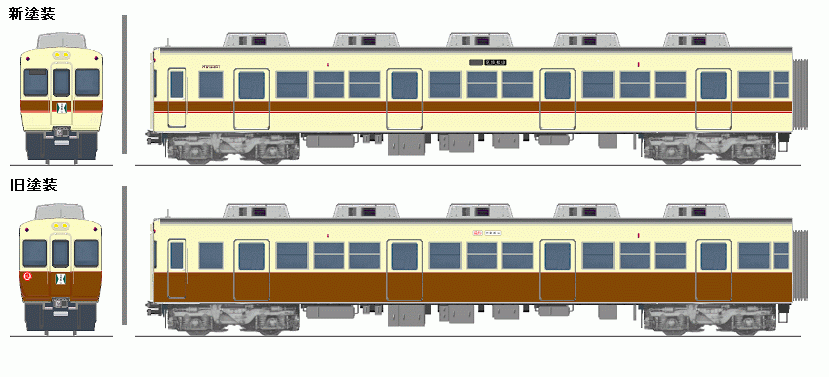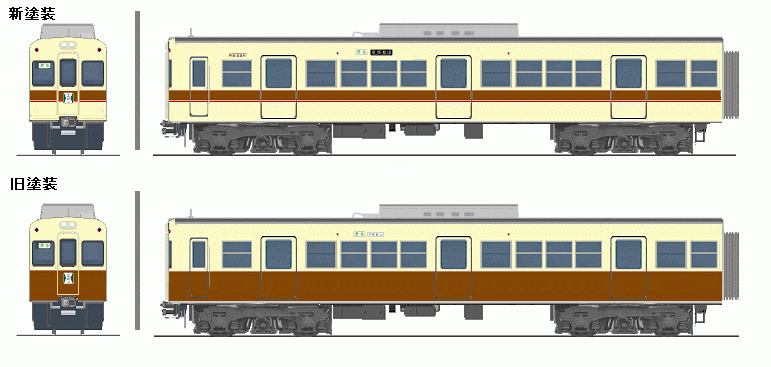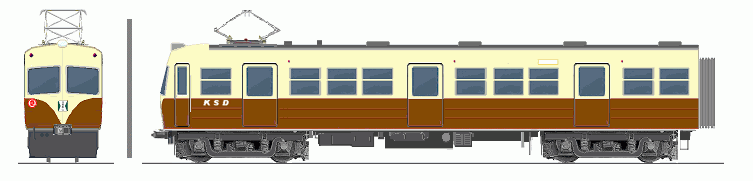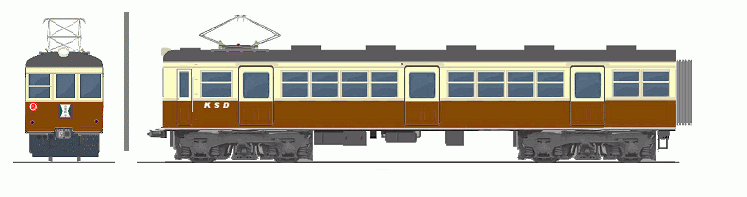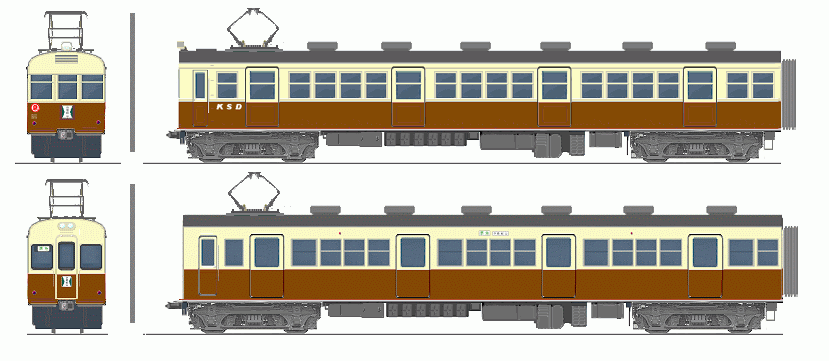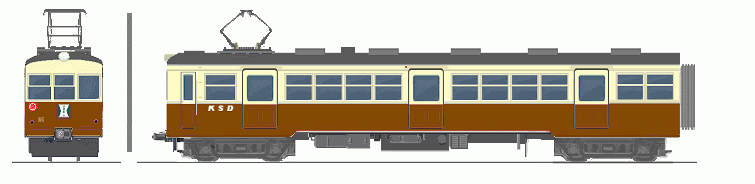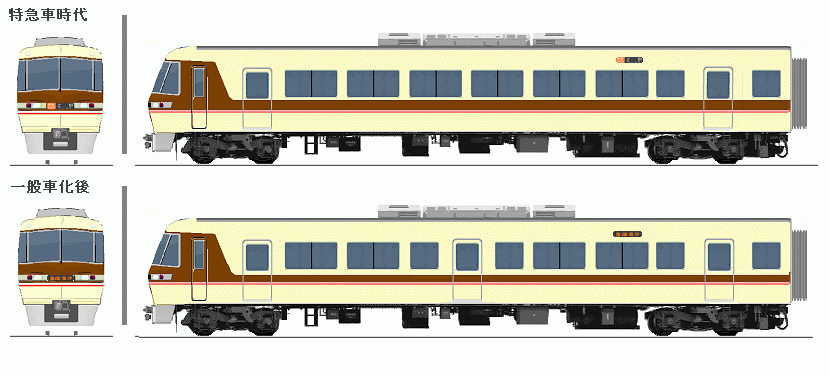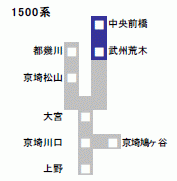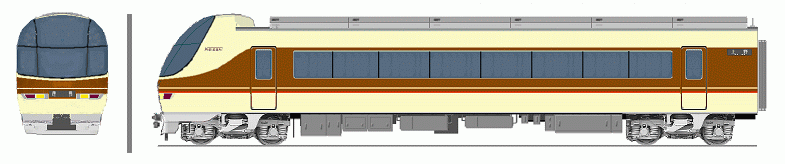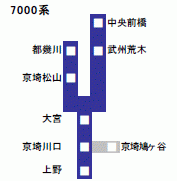[架空鉄道]
京埼電鉄 車両カタログ
※このページの内容はフィクションです。
 車両系の人、ごめんなさい。Web化に合わせて車両絵を描いてみました。
車両系の人、ごめんなさい。Web化に合わせて車両絵を描いてみました。
絵が下手なのと、十分な検証をしていないので、こんな感じというイメージで捉えてください。
台車に至っては、写真をハメ込んでいます。機器回りがあんまりわからないのでとりあえず、こんな感じ?としています。
各説明もツッコミどころ満載ですが、ご覧ください。
●引退車両
1630系 旧性能車 昭和22年 戦後多くの私鉄に導入された"63形"の京埼車。
1800系 旧性能車 昭和26年〜昭和56年 戦後の混乱期に登場した新造車。
2000系 高性能車 昭和32年〜昭和61年 湘南型の前面スタイル18m3扉
2700系 旧性能車 昭和初期〜戦前からの台車・機器を流用して製造された車両。
2800系 新性能車 行楽特急として登場した初の特急車両。
3000系 高性能車 昭和39年〜平成12年 上野延伸に伴う新時代を象徴する車両。
3100系 新性能車 1800・2000・2700系などの更新車両。
4000系 新性能車 地下鉄直通用車として登場、その後急行用として活躍した車両
●現役車両(一般車)
3500系
5000系
6000系
8000系
8500系
1500系
●現役車両(特急車)
7000系
京埼電鉄は、一般通勤形・特急形を問わず20m級の大型車両で統一している。
側面の基本スタイルは3500系以来変わらないものとして、素材の如何にかかわらず、
アイボリーにマルーン帯の塗装を施す「京埼流スタイル」としていた。
ステンレス車両が一般的な昨今、車両コストを抑える目的もあり、近代的な8000系を登場させた。
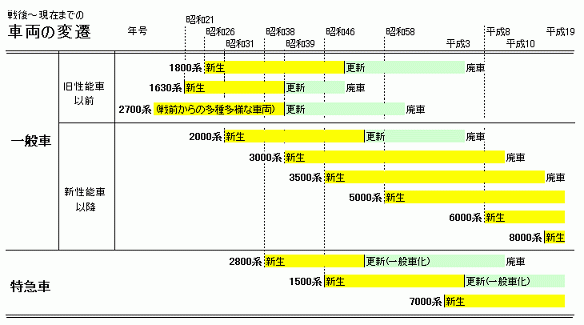
●8500系
平成25年、8000系に次ぐステンレス車両の導入に踏み切った。
駅間距離の長い線区や快速急行の運用として短編成を組み、異例の20m3扉車として登場した。
側面は8000系とほぼ同様のステンレス地に茶、赤帯、その隙間にアイボリーをわずかに残した。
| 車両イメージ |
 |
| 定期運用区間 | 基本諸元 |
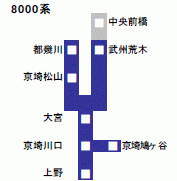
|
| 製造初年 | 平成25年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 3.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.5km/hs (非常時5.0km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 130km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:シングルアーム |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | 42000kcal/h,集中式1機 |
|
| 通風装置 | ラインフローファン |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,800mm |
| 車両寸法(高さ) | 4,030mm |
| 編成 | 6M4T |
| ドア | 両開き4扉 |
| 制御装置 | VVVF |
| 車内駅名表示装置 | LEDによる文字自動表示式 |
|
●8000系
老朽化の始まった3500系の置き換えとして、平成19年、京埼電鉄もいわゆる「通勤・近郊電車の標準仕様ガイドライン」
に沿った車両の導入に踏み切った。
10両編成のユニットを組むが、将来は短編成のユニットも登場させる構想もある。
前面のみ6000系と同じデザインを採用し、伝統的なアイボリーから一転、ステンレス地に茶、赤の帯を施し、
その隙間にアイボリーをわずかに残した。戸袋窓を廃止した。
| 車両イメージ |
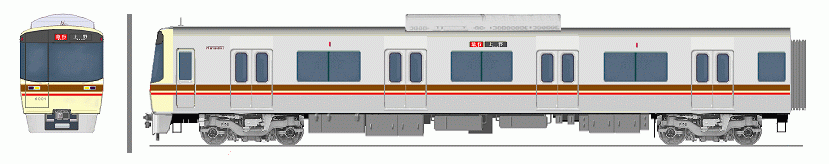 |
| 定期運用区間 | 基本諸元 |
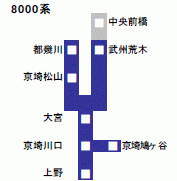
|
| 製造初年 | 平成19年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 3.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.5km/hs (非常時5.0km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 130km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:シングルアーム |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | 42000kcal/h,集中式1機 |
|
| 通風装置 | ラインフローファン |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,800mm |
| 車両寸法(高さ) | 4,030mm |
| 編成 | 6M4T |
| ドア | 両開き4扉 |
| 制御装置 | VVVF |
| 車内駅名表示装置 | LEDによる文字自動表示式 |
|
●6000系
京埼電鉄現在の通勤形標準車両。快速・急行での使用が多い。
平成に入り、初の左右非対称なデザインをはじめて採用した。
登場当初から8,10両編成のユニットを組むが、分割併合可能な4両+6両のユニットも存在する。
座席はパケットシートを初めて採用し、一人分の座席割り当てを明確にし、かつ居住性を高めた。
自動駅案内装置、自動放送、ドアチャイムを採用。
| 車両イメージ |
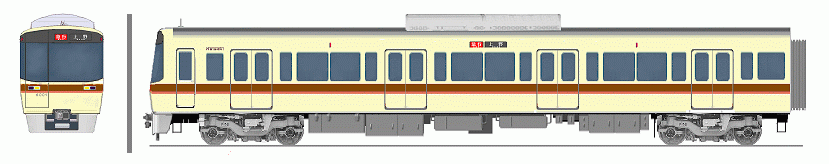 |
| 定期運用区間 | 基本諸元 |
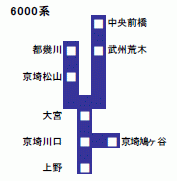
|
| 製造初年 | 平成8年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 3.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.5km/hs (非常時5.0km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 130km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形、シングルアーム |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | 42000kcal/h,集中式1機 |
|
| 通風装置 | ラインフローファン |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,800mm |
| 車両寸法(高さ) | 4,030mm |
| 編成 | 6M4T |
| ドア | 両開き4扉 |
| 制御装置 | VVVF |
| 車内駅名表示装置 | LEDによる文字自動表示式 |
|
●5000系
大宮駅地下化・大利根線直通運転に伴って大幅な増発が可能になったため、より高性能な車両が投入された。
「省エネ」をコンセプトに、サイリスタチョッパによる制御方式としている。
登場当時は4,6両のユニットとしていたが、後期には8〜10両の固定編成が登場した。
営団7号線(現:東京メトロ南北線)への乗り入れ構想があったため、その準備として後期形は
営団CS-ATCの取り付け準備、非常用貫通路の準備がなされている。
| 車両イメージ |
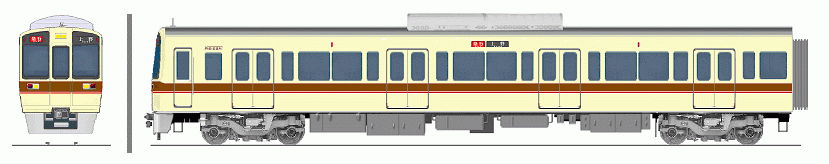 |
| 定期運用区間 | 基本諸元 |
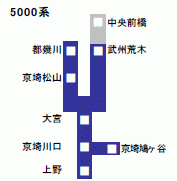
|
| 製造初年 | 昭和58年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 3.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.5km/hs (非常時5.0km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 130km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形、シングルアーム |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | 42000kcal/h,集中式1機 |
|
| 通風装置 | ラインフローファン |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,800mm |
| 車両寸法(高さ) | 4,030mm |
| 編成 | 6M4T |
| ドア | 両開き4扉 |
| 制御装置 | チョッパ/VVVF 1C8M |
| 車内駅名表示装置 | LEDによる文字自動表示式 |
|
●3500系
増大する通勤輸送に呼応するため当初から両開きドアを導入。
経済性を重視したため、各駅停車から急行までオールラウンドな運用に対応できるよう、
2,4,6,8とバリエーションに富んだ編成ユニットとしている。
運転台は人間工学に基づき、コンソールタイプになり初のワンハンドルマスコンを採用。
前面デザインは3000系のデザインを踏襲した妻面形。
時代に先駆けて一段下降窓を採用し、側面スタイルの基本は6000系まで踏襲されている。
初期生産の車輌は順次廃車が進んでいるが、昭和56年まで生産されたため系列別では車輌数が多く、
後期生産車は角型ヘッドライトに一部改められている。現在は各駅停車やローカル線区で使用されている。
| 車両イメージ |
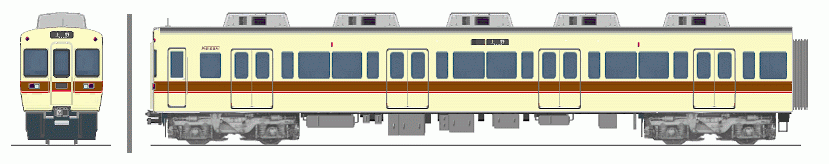 |
| 定期運用区間 | 基本諸元 |
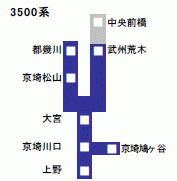
|
| 製造初年 | 昭和46年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 3.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.5km/hs (非常時5.0km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 130km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | 8,500Cal,分散式5機 |
|
| 通風装置 | ラインフローファン |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,800mm |
| 車両寸法(高さ) | 4,030mm |
| 編成 | 6M2T,4M2T,2M2T,2M |
| ドア | 両開き4扉 |
| 制御装置 | 抵抗/チョッパ 1C8M |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●3000系
上野地下駅乗り入れに合わせて登場した。
冷房装置、自動行先表示機、側面行先・種別表示機などの当時目新しいサービス機器が多く採用された。
3500系の登場に伴って、塗装の変更、前面に種別表示機の設置などを行い、京埼電鉄の車両史に一時代を築いた。
20m級の大型車輌であることに加え、車体幅に特急車サイズを採用し、ラッシュ時の乗客増に対応した。
晩年は、片開きドアであることから最混雑時を避けた運用に組み込まれたり、川口線、大利根線などのローカル線区で活躍したが、
6000系の増備に伴って2000年に全車廃車となっている。
| 車両イメージ |
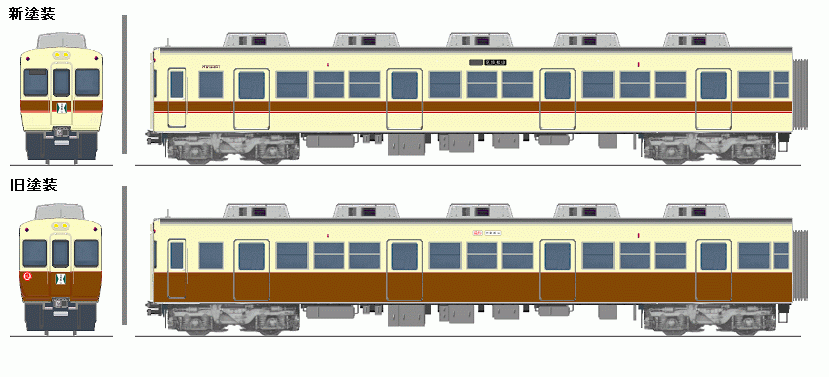 |
| 基本諸元 |
| 製造初年 | 昭和39年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 3.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.5km/hs (非常時5.0km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 120km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | 42000kcal/h,集中式1機 |
|
| 通風装置 | 扇風機 |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,800mm |
| 車両寸法(高さ) | 4,030mm |
| 編成 | 4M2T,2M2T,2M |
| ドア | 片開き4扉 |
| 制御装置 | 抵抗 1C8M |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●4000系
営団(現:東京メトロ)日比谷線直通用車両として製造された車両で、昭和39年に登場、3編成18両のみ存在した。
直通専用車として、規格もその規格に準じている。18m級、側面のドア窓配置もdD3D3D1となっているため、ドア位置が他の中型車とも異なって
いる。外装は当時標準的なアイボリーに茶胴の京埼の標準的な塗装であったが、これに独自に銀帯をまとった。地下鉄直通のための誤乗防止の
ためであった。加速度も東武、東急、営団の日比谷線用車に準じてオールM、4.0km/hsと高加速性能を持った。4両編成でデビューし、需要に応
じて中間車を増結する予定であった。
その後、直通運転の計画は頓挫し、上野-都幾川での急行運用専用車として2扉クロスシート化された。中央の窓が独特の形状をしているのはそ
の影響である。運転台付き中間付随車2両も増結し、6両編成で運用された。昭和57年以降は大利根線運用となり、平成13年に1500系にバトンタ
ッチをする形で廃車となった。
| 車両イメージ |
 |
| 基本諸元 |
| 製造初年 | 昭和39年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 3.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.7km/hs (非常時4.3km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 110km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | なし |
|
| 通風装置 | 扇風機 |
| 車長 | 18,000mm |
| 車幅 | 2,750mm |
| 車両寸法(高さ) | 3,920mm |
| 編成 | 2M |
| ドア | 両開き3扉 |
| 制御装置 | 抵抗 |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●3100系
伊奈新線の開業に合わせて、見劣りのする1800系、2000系、2700系などの旧性能車両を更新することになった。
足回りなどはほぼそのままに、3000系をモデルとして車体を新製したのがこの3100系である。
| 車両イメージ |
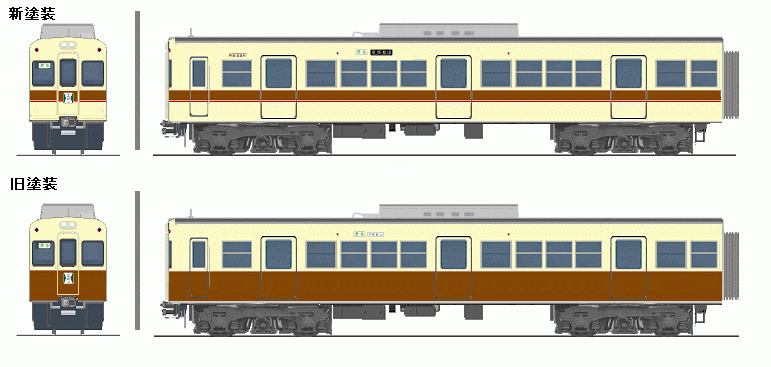 |
| 基本諸元 |
| 製造初年 | 昭和42年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 2.8km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.1km/hs (非常時4.3km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 110km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | なし |
|
| 通風装置 | 扇風機 |
| 車長 | 18,000mm |
| 車幅 | 2,550mm |
| 車両寸法(高さ) | 3,920mm |
| 編成 | 2M |
| ドア | 片開き3扉 |
| 制御装置 | 抵抗 |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●2000系
新時代を象徴する高性能車。
当時流行のカルダン駆動、2両ユニットのオールM車として誕生した。
晩年は武州荒木以北のローカル線区で活躍し、5000系の増備に伴って廃車となった。
| 車両イメージ |
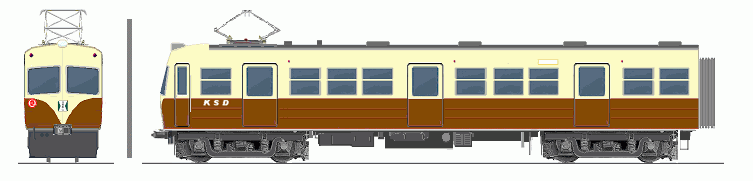 |
| 基本諸元 |
| 製造初年 | 昭和32年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 2.8km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.1km/hs (非常時4.3km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 105km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | なし |
|
| 通風装置 | 扇風機 |
| 車長 | 18,000mm |
| 車幅 | 2,550mm |
| 車両寸法(高さ) | 3,920mm |
| 編成 | 2M |
| ドア | 片開き3扉 |
| 制御装置 | 抵抗 |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●1800系
戦後は東武の影響もあり、火急の輸送力増強目的としての割当供給車63形の導入をすることになった。
苦心の末、一旦は20m4扉の大型車の導入を行ったが、元々小型車を基準とした車両限界によって、運転可能な区間が
限られていたため、大型車の本格導入には至らず戦後初の新造車は18mの中型車を導入することになった。
その後の近代化が完了し、3000系の導入によって、大利根線区(旧蓮田線)に大挙移籍した。
晩年は武州荒木以北の線区で活躍した。
| 車両イメージ |
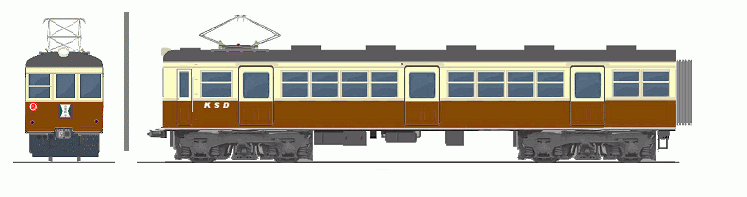 |
| 基本諸元 |
| 製造初年 | 昭和26年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 2.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 2.8km/hs (非常時3.9km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 95km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | なし |
|
| 通風装置 | 扇風機 |
| 車長 | 18,000mm |
| 車幅 | 2,550mm |
| 車両寸法(高さ) | 3,920mm |
| 編成 | 2M |
| ドア | 片開き3扉 |
| 制御装置 | 抵抗 |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●1630系
いわずと知れた統制会の63形であり、輸送力増強のために入線した車両であるが、
戦後の分離独立当時、京埼の路線の大半が元々小・中型車の設備規格であったり、カーブが多く、
大型車の入線が困難で、メインの本線都心部での使用ではなく、
導入しやすい本線の大宮-都幾川に限り、小・中型車を本線都心部へ移した。
3000系の登場の頃は本線での運転が可能となり、更新をおこなった。
冷房化されることもなく、昭和48年に全車廃車となった。
| 車両イメージ |
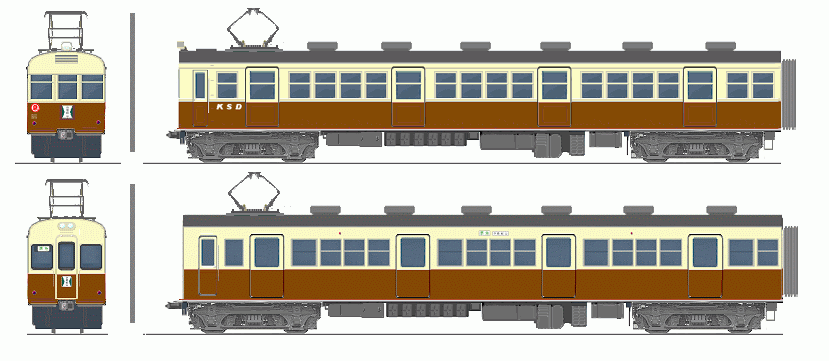 |
| 基本諸元 |
| 製造初年 | 昭和21年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 2.2km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.0km/hs (非常時3.8km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 95km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | なし |
|
| 通風装置 | 扇風機 |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,550mm |
| 車両寸法(高さ) | 3,920mm |
| 編成 | 2M |
| ドア | 片開き4扉 |
| 制御装置 | 抵抗 |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●2700系
戦前からの多種多様な旧型車両を流用し、車体を新製したのがこの車両である。
すべて18m3扉に統一され、1800系・2000系と運命をともにした。
3000系が登場すると、大挙蓮田線・大利根線に移籍した。
伊奈新線が開通すると、併せて導入された3500系と比較して見劣りすることなどから、
車体を新造し載せ替えられ、3100系として昭和61年まで活躍した。
| 車両イメージ |
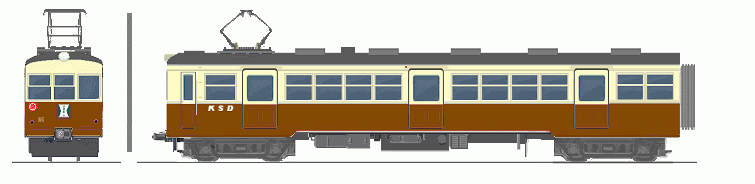 |
| 基本諸元 |
| 製造初年 | 昭和22年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 2.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.1km/hs (非常時4.3km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 95km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | ロングシート |
| 冷房装置 | なし |
|
| 通風装置 | 扇風機 |
| 車長 | 18,000mm |
| 車幅 | 2,550mm |
| 車両寸法(高さ) | 3,920mm |
| 編成 | 2M |
| ドア | 片開き3扉 |
| 制御装置 | 抵抗 |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●2800系
初代の特急車両。
昭和30年代の利根線は妻沼から東武熊谷線を経由して東京方面に向かうことができた。
乗客減が懸念されていた利根線・蓮田線の状況打開のため特急が新設され、特急専用車両として2800系が登場した。
ほとんどの便は蓮田-中央前橋の運転であったが、当時分断されていた本線との直通するべく国鉄東北線にも直通した。
本数は少ないものの下谷(上野)-大宮-蓮田-中央前橋の運転で、将来(当時)京埼が東京-前橋を結ぶアピールをするには充分であった。
オールクロスシート、特急車らしい設備としてはトイレのみであり、蓮田線での運転を行うため、車体長は小さめであり、4両編成で
運転された。2代目の特急が登場して以来は、内装などを更新しながら、団臨車として活躍した。
| 車両イメージ |
 |
| 基本諸元 |
| 製造初年 | 昭和38年 |
| 分類 | 特急車 |
| 車両性能(加速度) | 2.8km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.1km/hs (非常時4.3km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 120km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形 |
| 座席 | クロスシート |
| 冷房装置 | 3機 |
|
| 通風装置 | 扇風機 |
| 車長 | 18,000mm |
| 車幅 | 2,550mm |
| 車両寸法(高さ) | 3,920mm |
| 編成 | 2M |
| ドア | 片開き2扉または1扉 |
| 制御装置 | 抵抗 |
| 車内駅名表示装置 | なし |
|
●1500系
2代目の特急車両。
昭和53年、上野-中央前橋の直通特急運転開始に合わせて本格的な特急車両が誕生した。
7000系の登場に伴って、特急車としての役目を譲ったが、廃車とはならず、旅客サービスの向上として一般車化された。
6両編成を1ユニットとしていたが、編成の組替えも行われ、一部では中間車の先頭車化をし、3扉・座席シートなどの改造が加えられ、
京埼初のLED側面表示器を採用し、92年に再デビューを果たした。
大利根線武州荒木-中央前橋の各駅停車専用で、ワンマン運転が可能となっている。
| 車両イメージ |
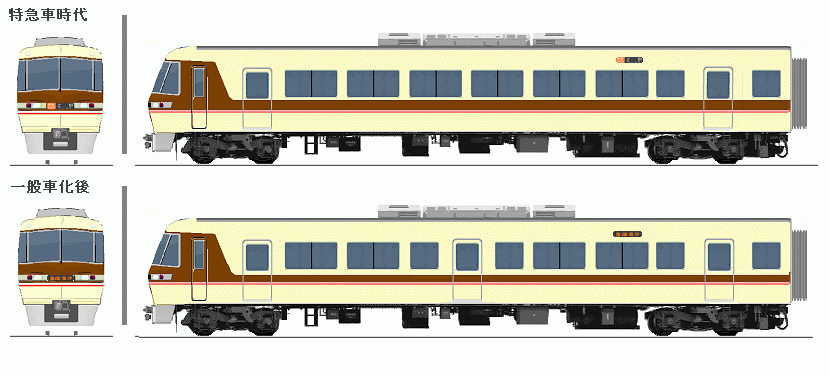 |
| 定期運用区間 | 基本諸元 |
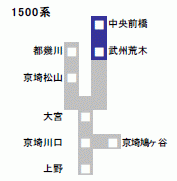
|
| 製造初年 | 昭和53年 |
| 分類 | 一般車 |
| 車両性能(加速度) | 2.8km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.1km/hs (非常時4.3km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 130km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形、シングルアーム |
| 座席 | 固定クロスシート(一部ロングシート) |
| 冷房装置 | 42000kcal/h,集中式1機 |
|
| 通風装置 | ラインフローファン |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,800mm |
| 車両寸法(高さ) | 4,030mm |
| 編成 | 2M |
| ドア | 片開き3扉 |
| 制御装置 | 抵抗 |
| 車内駅名表示装置 | LEDによる文字自動表示式 |
|
●7000系
現在の京埼を代表する特急車両。
通勤車両との併結も可能とし、20m級、6両編成で1ユニットを組む。
最先頭部は2階になっているが、上部が運転席、下部が客席になっている。
| 車両イメージ |
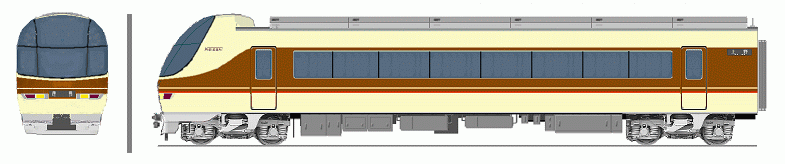 |
| 定期運用区間 | 基本諸元 |
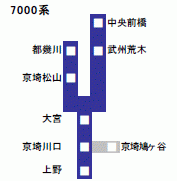
|
| 製造初年 | 平成4年 |
| 分類 | 特急車 |
| 車両性能(加速度) | 3.3km/hs |
| 車両性能(減速度) | 3.5km/hs (非常時5.0km/hs) |
| 車両性能(最高速度) | 130km/h |
| 連結装置 | 先頭側:自動連結器 中間部:半永久密着連結器 |
| 集電装置 | パンタグラフ:菱形、シングルアーム |
| 座席 | クロスシート |
| 冷房装置 | 42000kcal/h,集中式1機 |
|
| 通風装置 | ラインフローファン |
| 車長 | 20,000mm |
| 車幅 | 2,800mm |
| 車両寸法(高さ) | 4,030mm |
| 編成 | 6M4T |
| ドア | 片開き2扉 |
| 制御装置 | VVVF 1C4M |
| 車内駅名表示装置 | LEDによる文字自動表示式 |
|

 車両系の人、ごめんなさい。Web化に合わせて車両絵を描いてみました。
車両系の人、ごめんなさい。Web化に合わせて車両絵を描いてみました。 車両系の人、ごめんなさい。Web化に合わせて車両絵を描いてみました。
車両系の人、ごめんなさい。Web化に合わせて車両絵を描いてみました。