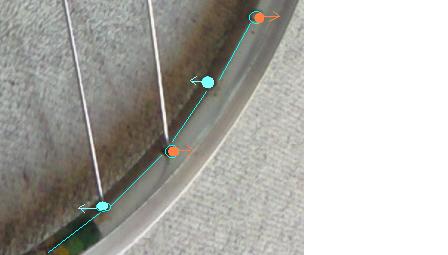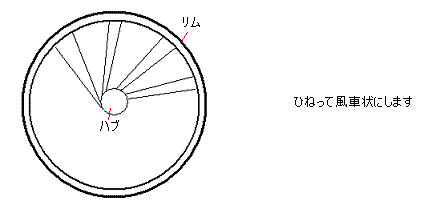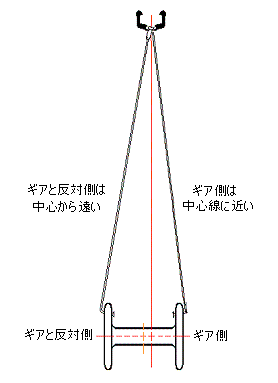MTBのホイールを組む 製作過程
MTBのホイールを組む 製作過程
2009.05.05作成
画像は写メなので、写りが良くないのはご容赦ください。
※組み立て過程を概略的に示したもので、詳細な組み立て方法は他サイトやショップなどで
確認してください。
愛車のマウンテンバイクを買ったのが、92年の1月。
もう17年も乗っていることになっていますが、
フレーム以外はパーツを交換しつつ、防犯登録もしなおして、乗り続けているのです。
パーツ交換のとき、毎回難儀するのが、スポークの張替えです。

今回はダメージの激しい後輪のスポークを張り替えることにしました。
スポークを組むときに、ホイール組み立てキットのマニュアルを読んでいくのですが、いまいちよくわからなかったりする…。
というわけで備忘録を兼ね、画像付きで組み立ての製作過程を示してみます。
準備するもの
 【パーツ】
【パーツ】
・スポーク
・ニップル
・リム(写真にはありませんが)
・ハブ(写真にはありませんが)
------------------------------
【工具類】
・ホイール組み立て台
・ニップルまわし
・マイナスドライバー
・ノギス(写真にはありませんが)
・メジャー
スポークの長さ計算
なにはともあれ、必要なスポークの長さを計算します。
当たり前の話ですが、スポークは"26インチ用"とかではなく、ミリ単位で売っています。
ショップとかで購入できますが、たいがいは注文することになるため、私はネット通販で購入しました。
で、注文する前に、どの長さが適合するのか。
ハブの大きさなども影響するため、事前にリムやハブの長さ・径などを測定して計算します。
この計算が結構面倒で、厄介だったりしますので、スクリプトで自動計算するようにしました。
スポーク、ニップルの材質はスチールやステンレスなどがありますが、今回はステンレスのものを使用することにしました。
リムのチェック
今回はリアのホイール作成ですので、左右の長さがことなる、おちょこ組みのスポークテンションになります。
組み立ての前に、若干チェックをしておきます。
↓チェックとしてはこんなところでしょうか。
・リムの変形がないかどうか。平坦なところ、テーブルの上などにおいたり、ガラス窓に押し当てりして、
変形がないかを確認します。平坦な場所に置く場合は、一端を指で押してみて、反対側が浮き上がら
ないか、5mm以上の浮き上がりであれば、歪んでいますので、使用は控えたほうがよさそうです。
リムの変形は癖として残ってしまうことがあり、振れの原因にもなります。
・リムの孔数を確認します。ハブとスポークの孔の数に問題がないかを確認します。
・リムのスポーク孔をウエスなどで拭いて、汚れを落としておきます。
<注意>ニップルのネジ切りはゆるくなりやすく、一度締めたら、緩めないようにしてください!
ハブのチェック
前輪用のハブの場合はどちらでもかまいませんが、後輪のハブの場合は、まずギア側を下にします。
このときのハブのフランジにあいている上下のフランジのスポーク孔は同じ垂線にあるわけではなく、
半ピッチずつずれているのを確認します。
スポークをハブに通します
ギア側を下にしてハブを立てて持ったら、まず上側(ギア側の逆)のフラン時の上面から1つおきにスポーク
を差し込んでいきます。
フランジのスポーク孔を通ったスポークは、下側(ギア側)の孔には通さず、自然に垂れ下げておきます。(↓下の写真)

スポークをリムの通します
①まずリムにあいているバルブ孔の左隣のスポーク孔に1本のスポークを通し、先端のネジ部分にニップルを
ねじ込んで(仮止め)リムから外れないようにしておきます。(↓下の写真)

② ①のスポークからみて左隣のスポークを、次は今差し込んだスポーク孔から、写真のように3つスポーク孔を
とばして、4つ目の孔に差し込みます。(↑上の写真)
これもまた、リムから外れないようにしておきます。
このようにして、9本のすべてのスポークをリムに通すと、スポークは放射状になります。
(↓下の写真)

反対側のスポークをハブに通します
次に、仮組みしたホイールをひっくり返して、反対側のスポークを組みます。
③ ①と同じようにフランジの上面から1つ孔おきにスポークを差し込み、ハブの縁に垂れ下げます。
(↓下の写真)
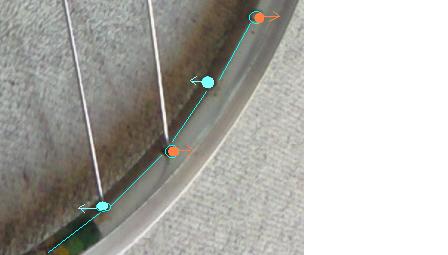
反対側のスポークをリムを通します
④ ②と同じようにスポークをリムに通して、ニップルで仮止めします。
このとき既に通してある反対側のハブから出たスポークのすぐ左隣りのスポーク孔に通していることを確認
しないといけません。これが隣り合っていないと、リムのスポーク孔が、ギア側→ギア側→逆側→逆側→ギア側→・・・
となってしまうためです。ギア側→逆側→ギア側→逆側→ギア側→・・・となるのが正解です。(↓下の写真)
18本ともすべて通した後にホイールを上から見ると、2本ずつのスポークがペアになりながら放射状に張ってある
ことがわかります。
上側のハブフランジから出ているスポークが、左側に差し込んであり(↓下の写真で水色の●)
下側のハブフランジから出ているスポークが、右側に差し込んである(↓下の写真で橙色の●)
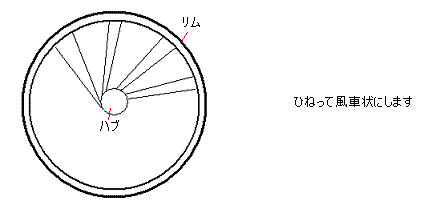
ハブをねじります。
⑤クロス組の準備のため、リムはそのままに、ハブだけを時計と逆方向にねじります。
スポークがねじられて風車状になりますが、この形が基本になります。
指で軽くニップルを締めるなどして、孔からニップルが出るようにします。
押し込んだりニップルを軽く締めたり、ハブをしっかりひねったりするなどして、
すべてのニップルがしっかり孔から頭を出すようにしないと、この後の作業でスポークが届かなくなります。
スポークをクロスに組みます(ギア側)
⑥さて、いよいよ作業も佳境にはいりました。
ハブのギア側が上になったままの状態で、上側のフランジに内面からスポークを差し込みます。いっぱいまで
引き上げた後、左側(④とは放射する向きが逆方向)へ倒していきます。
今差し込んだスポークの隣のスポーク孔を1つ目として、左へ5つ目の孔から出ているスポークの下をくぐり
そのスポークがとまっている2つ左の空いている孔にスポークを差し込み、ニップルで仮止めしておきます。
このときに、④で差し込んだときに仮止めしたニップルと、⑥のニップルが同じ分だけ出ているようにします。
ホイールを組むときに重要な均等な作業にならなくなるためで、後の振れ取り段階でやると、歪な力が加わり、
チューニングがしづらくなるからです。
9本通しおわったら、ハブを軽くゆすったり、ニップルがリム孔から抜けて内側に頭がでているかどうかを
確認しておきます。
スポークをクロスに組みます(ギアと逆側)
⑦次にホイールを反対側に返して、ギアと逆側のスポークも⑥と同じように組んでいきます。
ただし、⑦では引き上げたスポークは今度は右に倒していくのが違いです。
組みあがったら、ホイールの回転角に対して鈍角になる左右のスポークは外側に、鋭角になる左右のスポークは
内側になっていることを確認してください。
これでホイールの仮組みは完了です。
オチョコ組み(オフセット組み)
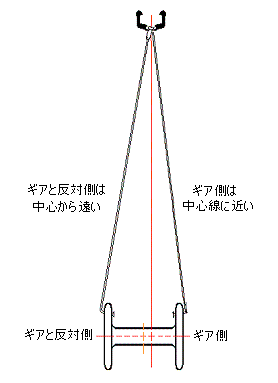
前輪(フロント)の場合は、左右のスポークを均等に
張ればよいのですが、後輪(リア)の場合は、ホイール
を縦断する中心線に対して左右均等な位置になく、
ギア側のフランジは中心に寄ったところにあります。
これを「オチョコ組み」(オフセット組みとも)といいます。
オチョコ組みをすることで、ホイールにかかる力(トルク)は、
ギア側に対してかかってきます。
ギア側のスポークのほうが反対側に比べて、より直角に
張られてしまうからです。
それゆえ、ギア側のスポークをしっかり正しく調整されて
いれば、振れが出にくいメンテナンスフリーなホイール
になります。
スポークを張っていく
ホイールを振れ取り台にセットし、振れ取り台の中心に沿って、まっすぐに取り付けられていることを
確認します。ひとまず、ニップルのねじ込み量を同じ分だけにし、ニップルが孔からでるように調整するなど
します。
リムをゆっくりと回転させながらスポークのニップルを少しずつまわし、振れている箇所を探します。
振れている側にテンションが強くかかっているので、逆側のニップルを締めることで振れがなくなっていきます。


 MTBのホイールを組む 製作過程
MTBのホイールを組む 製作過程
 【パーツ】
【パーツ】